未来酒店オンラインストア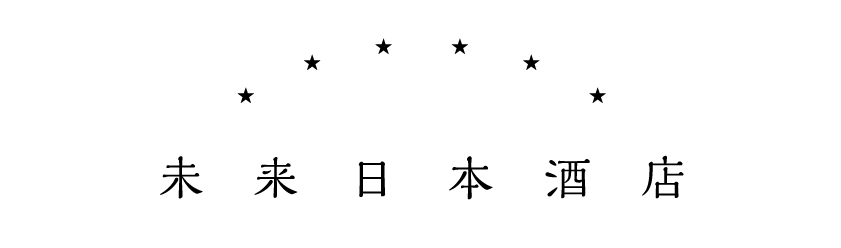
ストアアクセス
Opening soon
一時的にサイトを非公開とさせていただきます。 既存のご注文に関するお問い合わせは、弊社の渋谷店までご連絡ください。 03-6455-3975 shibuya@miraisake.com
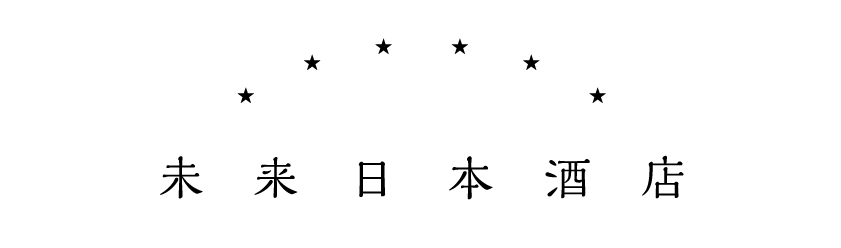
ストアアクセス
Opening soon
一時的にサイトを非公開とさせていただきます。 既存のご注文に関するお問い合わせは、弊社の渋谷店までご連絡ください。 03-6455-3975 shibuya@miraisake.com